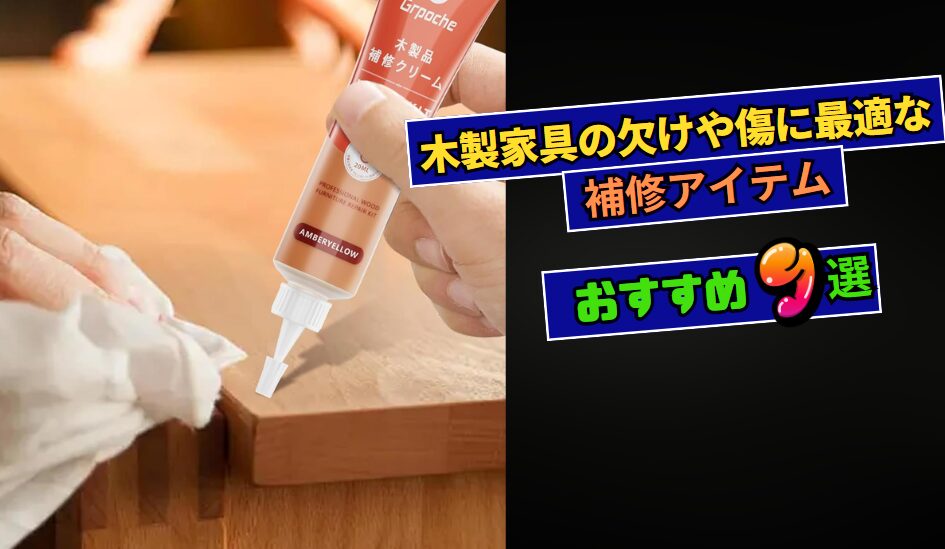
木製家具は、長く使うほどに味わいが増す一方で、小さな欠けや傷が気になってしまうこともあります。
そんなときに役立つのが、自宅で手軽に使える「補修材」です。用途や仕上がりの違いに応じて選べば、大切な家具を自分の手で美しくよみがえらせることができます。
この記事では、木製家具の欠けや傷に対応できる補修材の種類と、それぞれの特長や選び方、使用時のポイントを詳しく解説したうえで、おすすめの商品を厳選してご紹介いたします。
この記事でわかること
- 木製家具の傷に適した補修材の種類と特徴
- 補修材ごとのメリット・デメリット
- 自然に仕上げるための選び方と使い方のコツ
- 補修に使えるおすすめ商品
Contents
木製家具の欠けや傷に最適な「補修アイテム」おすすめ9選
木製家具の欠けや傷を自分で補修する際、仕上がりの美しさや作業のしやすさは「補修材選び」に大きく左右されます。
ここでは、DIY初心者でも使いやすく、評価の高いおすすめの補修商品をご紹介します。
補修の目的や傷の深さに合わせて最適なタイプを選べば、家具を新品のように蘇らせることができます。費用を抑えつつ、しっかりと補修したい方はぜひ参考にしてみてください。
SEISSO 家具補修クレヨン 10色セット
木製家具やフローリングの傷補修に便利なクレヨンタイプのセットです。10色入りで、さまざまな木材に対応できるため、自然な色合いで傷をカバーできます。環境に優しい素材を使用しているため、安全性も確保されています。
使い方は簡単で、補修箇所にこすりつけるだけ。DIY初心者でも扱いやすく、専門業者を頼まずに済むためコスト削減にもつながります。家庭のメンテナンスに役立つ便利なアイテムです。
SEISSO 木製品キズ補修クリーム 12色セット
柔らかく伸びが良いクリームタイプの補修材で、木製家具やフローリングの傷を自然にカバーできます。12色入りで混色も可能なため、さまざまな木材やインテリアに合わせやすく、色合いの調整も自由自在です。
環境に優しい素材で作られているため、安全に使うことができます。乾燥後も色褪せしにくく、補修後の美しさが長続きします。簡単な操作でDIY補修ができ、プロに頼る必要がないためコスト面でも安心です。
Grpoche 補修クリーム 12色入り
無毒で安全性が高く、木製家具やフローリングの傷補修に最適なクリームタイプのセットです。12色の豊富なカラーバリエーションがあり、複数色を混ぜて微妙な色合いを作ることができます。
柔らかなテクスチャーで塗りやすく、細かい傷やへこみにもしっかり密着。補修後は自然な仕上がりになり、家具や床が新品同様に蘇ります。使い方が簡単で、コストを抑えつつ効果的に補修できるため、DIY初心者にもおすすめです。
SEISSO 木製品キズ補修クリーム 18色&補修ペンセット
18色の補修クリームと8色の補修ペンがセットになった多機能キットです。木製家具やフローリングの傷や凹みをしっかりとカバーし、補修後も自然な色合いを実現します。
色を混ぜて自分好みの色を作れるため、木材の色合いが異なる場合でも調整が簡単です。さらに、補修ペンを使えば木目の表現もでき、美観を損なわずに仕上がります。DIYで本格的な補修ができるため、プロに頼らずにコストを抑えられます。
SEISSO 補修クリームキット 24色入り
24色の補修クリームがセットになっており、家具やフローリングの色に合わせやすいのが特徴です。ブラシやスクレーパーが付属しているため、クリームの塗布や仕上げが簡単にできます。
色を混ぜ合わせて使用することで、複雑な木目や色合いにも対応可能です。DIY初心者でも手軽に使える設計で、プロに頼まずに補修できるため、時間やコストを節約できます。補修後は自然な仕上がりで、木製品が新品のように蘇ります。
DEWEL フローリング リペアキット 電気ゴテ付き
電気ゴテを使った瞬間硬化式の補修キットです。11色のワックスブロックがセットになっており、色を混ぜ合わせて微妙な色合いを作ることができます。電気ゴテを使うことでワックスがすぐに溶け、ひび割れや穴を素早く埋められます。
乾燥後はサンディングで仕上げれば、滑らかで自然な見た目に。操作が簡単なため、DIY初心者でもプロ並みの補修が可能です。耐久性のある仕上がりで、頻繁なメンテナンスを避けたい方におすすめです。
IMPACTオンライン フローリング補修ワックス 11色セット
11色のワックスが揃った大容量リペアキットです。色合わせがしやすく、白色でトーンを調整できるため、さまざまな床色に対応可能です。初心者でも使いやすい設計で、ワックスを傷や凹みに塗り込むだけで簡単に補修できます。
大容量で繰り返し使えるため、広範囲の補修にも最適です。傷やへこみが目立たない自然な仕上がりになり、フローリングや家具が蘇ります。コストを抑えながら、きれいに補修できるアイテムです。
コモライフ キズかくしマルチカラーペン 6色セット
木製家具やフローリングの細かい傷補修に便利なマーカータイプのセットです。6色入りで、色を混ぜて自然な仕上がりが得られます。太描き・細描き両方に対応するペン先を採用し、使い勝手が抜群です。
サッと塗るだけで色がなじみ、手軽に補修が完了します。特に軽度の傷や色剥げ部分に効果的で、補修後は家具や床が美しく蘇ります。日本製で品質も安心、家庭でのちょっとした補修に最適です。
木製家具補修マーカー&クレヨン 17個セット
リペアマーカー8本とクレヨンスティック8本がセットになった便利な補修キットです。オーク、マホガニー、ブラックなど多彩な色が揃っているため、木製家具やフローリングの色に合わせて自然に補修できます。
ペンタイプで細かい傷も描きやすく、クレヨンで凹みを埋めることで、目立たない仕上がりが実現します。環境に優しい素材を使用し、体に害がないため安心して使えます。簡単な操作で美しい補修ができる優れたアイテムです。
木製家具向け「補修材」のメリット

パテタイプ:強度が高く、補修後の耐久性がある
パテタイプは、木製家具の欠けや大きな凹みをしっかりと補修できるのが特徴です。理由は、硬化後に固まるため、家具本体と一体化しやすく、衝撃や圧力に強くなるからです。これにより、耐久性が高まり、長期間にわたって補修箇所が崩れにくくなります。
例えば、テーブルの角が欠けてしまった場合でも、パテを使って補修すると、しっかり固定されて剥がれにくくなります。特に、重い物を載せる机や椅子など、強度が求められる家具に適しています。パテは、乾燥後に塗装や研磨ができるため、仕上がりも自然に見せることができます。
クレヨンタイプ:手軽に使え、即座に色合わせができる
クレヨンタイプの補修材は、初心者でも簡単に使えるのが魅力です。欠けた部分や細かい傷に直接こすりつけるだけで、すぐに色がなじみます。力を入れずに塗るだけで補修できるため、作業が手軽でスピーディーです。
例えば、フローリングの表面にできた小さな傷や、引き出しの角が擦れて色が落ちた部分に使うと、すぐに色が戻ります。色数が豊富で、家具の色に合わせて選べる点も便利です。
ワックスタイプ:表面を滑らかにし、自然な艶を出せる
ワックスタイプの補修材は、木製家具の艶出しや細かい擦り傷のカバーに優れています。塗るだけで表面が滑らかになり、木目が美しく引き立つため、見た目をきれいに仕上げたいときに最適です。
例えば、ダイニングテーブルの表面が擦れてツヤがなくなってしまった場合、ワックスを塗ると元の光沢が戻ります。特に、自然な木の風合いを損なわずに艶を出すことができるため、アンティーク調の家具や無垢材のケアに適しています。
木製家具向け「補修材」のデメリット
パテタイプ:硬化に時間がかかり、乾燥後に縮むことがある
パテタイプの補修材は、欠けた部分をしっかりと埋められるため、強度が高いのが特徴です。しかし、その反面、硬化に時間がかかるため、作業完了までに余裕を持つ必要があります。特に、湿度や気温の影響で硬化が遅れることがあり、乾燥が不十分な状態で触れると補修が台無しになってしまうリスクもあります。
さらに、パテタイプは乾燥後に若干縮むことがあり、補修箇所が凹んでしまうことがあります。そのため、適量を考慮して少し多めに塗布し、乾燥後にヤスリで表面を整えるのがコツです。強度を求める際には適していますが、短時間で補修を終えたい場合には向いていません。
これらの点から、パテタイプを使用する際は、乾燥にかかる時間や縮む可能性を考慮し、丁寧に作業を進めることが重要です。
クレヨンタイプ:強度が低く、深い欠けには不向き
クレヨンタイプの補修材は、手軽さと使いやすさが魅力です。傷に直接こすりつけるだけで簡単に色がつき、すぐに見た目を整えられるため、忙しい時でも便利です。しかし、強度が低いため、深い欠けや大きな凹みには適していません。
特に、家具の角が大きく欠けている場合や、頻繁に触れる部分には不向きです。塗布後も柔らかさが残り、強い衝撃や摩擦で剥がれやすいという欠点があります。例えば、椅子の脚やドアノブ周辺など、頻繁に触れる部分にはすぐに剥がれる可能性が高まります。
クレヨンタイプは、小さな傷や軽度の色落ちを一時的にカバーする用途として使うと便利です。しっかりした補修を求める場合には、他の補修材を検討すると良いでしょう。
ワックスタイプ:熱に弱く、強度が低いため頻繁な補修が必要
ワックスタイプの補修材は、木製家具の表面を滑らかにし、自然な艶を出すために使われます。ただし、熱に弱い性質があるため、直射日光が当たる場所や熱源の近くでは溶けやすく、補修した部分が崩れやすいです。
また、強度が低いため、物を頻繁に置くテーブルや、ペットが爪を立てやすい床には適しません。一度補修しても、触れるたびに剥がれてしまうリスクがあり、何度もやり直す必要が出てきます。そのため、補修の頻度が多くなりがちです。
ワックスタイプは、見た目をきれいに整えるために使うと効果的ですが、衝撃や摩擦が加わりやすい場所には向きません。艶を出したい家具や、飾り棚のように触れる機会が少ない部分に使うと良い結果が得られます。
木製家具向け「補修材」の選び方

周囲の色と近い色を選ぶと自然に見える
木製家具の欠けを補修する際には、周囲の色にできるだけ近い色の補修材を使うことがポイントです。色が合っていないと補修部分が目立ってしまい、かえって不自然になってしまいます。これを防ぐためには、家具の色をしっかり確認し、似た色味の補修材を選ぶことが大切です。
特に、ダークブラウン系の家具にはウォールナットやマホガニー色、ライトブラウン系にはオークやナチュラルウッド色が合いやすいです。色見本が付属している補修キットを使うと、失敗を減らせます。
補修材を選ぶ際には、必ず家具の色と照らし合わせて確認しましょう。光の当たり具合によっても色味が異なるため、自然光の下でチェックするのがベストです。これだけで補修跡が格段に目立たなくなります。
複数色を混ぜて微調整するとより馴染む
木製家具は、ひとつの色では表現できない複雑な色合いを持っていることが多いため、補修材も複数色を混ぜて使うことで、より自然に仕上げることができます。これにより、補修後の違和感が軽減され、木目と一体化したように見せられます。
例えば、明るいブラウンに少量のダーク色を混ぜると、深みのある色が作れます。補修キットには複数色がセットになっていることが多いため、まずパレットなどに少量ずつ出して混ぜながら確認しましょう。
混色をする際には、薄い色をベースにしながら少しずつ濃い色を加えると、失敗が少なく済みます。また、色が合っているかどうかは、補修する部分の近くでテストして確認すると安心です。
透明タイプや自然木色が使いやすい
木製家具の補修材を選ぶときには、透明タイプや自然木色の製品が使いやすいです。理由は、これらの色が木の風合いを損なわず、どのような家具にも比較的なじみやすいからです。特に、無垢材やナチュラルカラーの家具では、透明なワックスや自然木色のパテが適しています。
透明タイプは、表面を滑らかにして艶を出す効果があります。木目が透けて見えるため、木材そのものの質感を活かした補修が可能です。自然木色は、ほぼ元の色に近いため、補修跡が目立ちにくいです。
ただし、透明タイプだけでは色味を補えないため、色付きの補修材と併用することがポイントです。家具の色合いに合わせて、透明と自然木色を使い分けると、より自然な仕上がりになります。
木製家具向け「補修材」の使用ポイント

汚れやほこりをしっかり取り除く
木製家具の欠け補修を行う際には、まず汚れやほこりをしっかり取り除くことが大切です。汚れが残ったままだと、補修材がうまく密着せず、補修後に剥がれやすくなってしまいます。特にフローリングやテーブルの表面には、油分や埃が付着していることが多く、そのまま作業を始めると補修効果が半減します。
汚れやほこりを取る際は、乾いた布や掃除用クロスで丁寧に拭き取ることが基本です。水拭きができる場合は、中性洗剤を薄めた布で軽く拭き、その後は必ず乾いた布で水分をしっかり取り除きましょう。湿気が残っていると、補修材が浮いてしまい、仕上がりが悪くなります。
また、溝や細かい部分には、ブラシや掃除機を使うと効果的です。特に傷が深い場合には、汚れが入り込んでいることが多いため、根気よく掃除を行うことが大切です。
表面を軽く研磨し、補修材が密着しやすくする
補修材を使う前には、補修箇所の表面を軽く研磨することが重要です。表面がざらついていると、補修材がうまく乗らずに剥がれやすくなります。特に、古い塗装が残っている場合や、削れた木のささくれがあると、仕上がりが不自然になるため注意が必要です。
強くこすりすぎると、逆に傷を増やしてしまうため、軽い力で表面を均一に整えましょう。研磨後は、削り粉や細かい木くずをしっかりと取り除くことがポイントです。これを怠ると、補修材が粉に絡んでしまい、綺麗に仕上がりません。
平らに整えた表面に補修材を使うことで、密着力が向上し、補修後も剥がれにくくなります。特にパテタイプの場合、研磨をしっかり行うことで、乾燥後の安定感が増します。こうした下準備をきちんと行うことが、長持ちする補修のコツです。
パテは少量ずつ埋め、均等にならす
パテタイプの補修材を使うときには、少量ずつ埋めることが成功のポイントです。一度に大量に盛ると、乾燥後に縮んで凹んでしまったり、ひび割れが発生するリスクが高まります。補修箇所に合わせて、適量を何度かに分けて塗布しましょう。
使用する際は、ヘラやスパチュラを使って、パテを少量ずつ取り、欠けた部分に押し込むように塗ります。力を入れすぎると押し出されてしまうため、優しく均等に広げるのがコツです。塗り重ねる場合には、一層目がしっかり乾いてから次の層を塗るようにします。
乾燥後には、表面が凸凹していることが多いため、紙やすりで滑らかに仕上げます。この工程を丁寧に行うことで、塗装時に違和感が出にくくなり、自然な見た目に仕上がります。パテの量や塗り方を工夫し、均等な仕上がりを心がけることで、補修箇所が目立たなくなります。
乾燥後に研磨し、表面を滑らかに整える
補修材がしっかり乾いた後には、表面を研磨して滑らかに整える工程が必要です。乾燥後、そのまま放置すると表面がザラザラしたり、色ムラが発生しやすくなるため、仕上げ研磨が欠かせません。
使う研磨紙は#400〜#600程度の細かいものが適しています。強く削りすぎると補修箇所が剥がれる恐れがあるため、軽い力で均一にこすることがポイントです。
研磨が終わったら、布で削り粉を丁寧に拭き取ります。こうすることで、次の塗装工程がスムーズに進み、仕上がりがより美しくなります。研磨作業を怠らず行うことで、家具全体の質感が整い、補修箇所が自然に馴染みます。
艶出しワックスで最終仕上げすると高級感が増す
補修作業の最後に、艶出しワックスを使うと家具全体の仕上がりが格段に向上します。ワックスを塗ることで、木の自然な光沢が引き立ち、補修箇所も目立たなくなります。特に、高級感を求める場合には、この仕上げ工程が効果的です。
ワックスを使用する際は、柔らかい布に少量を取り、木目に沿って薄く塗り広げます。厚塗りするとムラになりやすいため、何度かに分けて塗るのがポイントです。塗り終えたら、乾いた布で軽く磨くと艶が出て、美しい仕上がりになります。
艶出しワックスは、ダイニングテーブルやサイドボード、飾り棚など、人目に触れる家具に使うと、より効果が感じられます。ただし、ワックスは熱に弱いため、熱い鍋やコップを直接置かないよう注意しましょう。ワックス仕上げを定期的に行うことで、木製家具の美しさを長くキープできます。
まとめ:木製家具の欠けや傷に最適な「補修アイテム」おすすめ9選
木製家具の欠けや傷は、使い続ける中でどうしても避けられないものです。しかし、正しい補修材を選び、適切な手順でケアすれば、自分の手で見た目も機能も美しく蘇らせることができます。
今回の記事では、補修材の種類ごとの特徴や選び方、使い方のポイントまで詳しく解説しました。最初は難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえれば初心者でも十分に対応できます。
大切な家具を長く愛用するためにも、日常のメンテナンスとともに、ちょっとした傷も自分で直せる知識と道具を備えておくと安心です。








