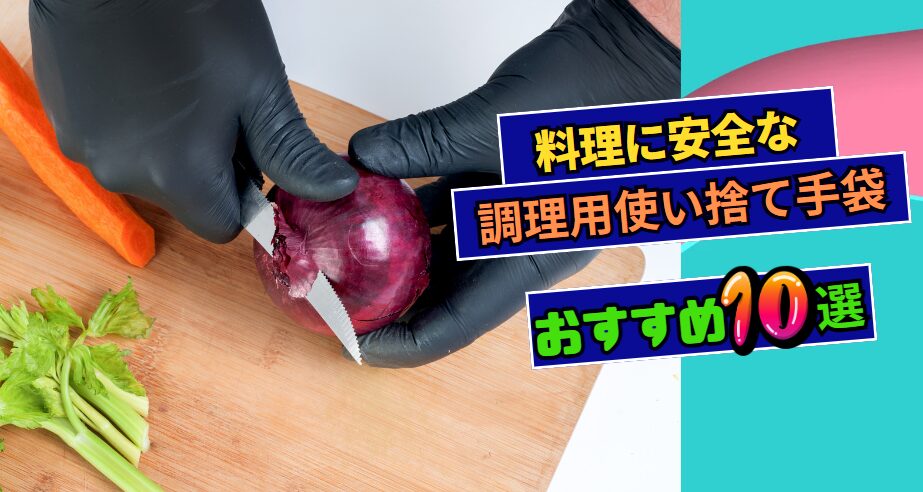
日々の調理を衛生的かつ快適に行うために欠かせないのが、調理用手袋です。手袋を着用することで、食材への雑菌の付着を防ぎ、手荒れやにおい移りなどのトラブルも軽減することができます。
この記事では、衛生面・機能性・使いやすさの観点から厳選した調理用手袋のおすすめをご紹介いたします。
あわせて、選び方のポイントや注意点、正しい使い方についても丁寧に解説しています。ご自身の調理スタイルに合った最適な一枚を見つける参考になれば幸いです。
この記事でわかること
- 調理用手袋を使うメリットとデメリット
- 素材やサイズなど選び方のポイント
- 衛生的に使うための正しい使い方
- おすすめの調理用手袋
料理に安全な「調理用使い捨て手袋」おすすめ10選
まずここでは、家庭でも業務用でも使いやすく、信頼性の高い調理用手袋を厳選してご紹介します。
耐久性、フィット感、使いやすさなど、選ぶ際に重視したいポイントを踏まえて、実際の使用シーンを想定しながら選定しています。
あなたのキッチン環境や目的に合った一枚がきっと見つかるはずです。
ショーワグローブ ニトリストタッチ No.882(100枚)
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しており、調理をはじめ、掃除やメンテナンス、園芸など幅広い用途に対応します。
パウダーフリーで衛生的、ラテックスフリーのためアレルギーが心配な方にも安心してご使用いただけます。
Amazonブランド Presto! ニトリル手袋(200枚)
素手感覚で細かい作業ができるフィット感に優れた手袋です。調理や掃除、介護などの日常作業から、油汚れを扱う業務用まで幅広く活躍します。
左右兼用でムダなく使え、パウダーフリーで肌にもやさしい設計。スマホ操作にも対応しており、作業効率も高まります。
SANYU ニトリル手袋 ブラック(100枚)
厚手設計で破れにくく、指先には滑り止め加工が施されています。フィット感が高く、調理や清掃、介護などの細かい作業にも適しています。
ラテックスフリーでアレルギーの方にも配慮されており、食品衛生法にも適合。高い耐久性でコスパも良好です。
SANYU ニトリル手袋 ブルー(100枚)
弾力性がありながら丈夫な厚手のニトリル手袋です。食品衛生法に適合し、料理や食品加工などの衛生管理が必要な場面でも安心して使用できます。
指先の感覚を活かした作業ができるため、細かい工程が多い作業にも適しています。着脱もスムーズです。
極うす手ニトリル手袋 ホワイト(100枚)
極薄タイプで手にぴったりフィットし、素手のような感覚で作業ができます。粉なしタイプで肌への刺激が少なく、着脱もしやすい仕様です。
食品衛生法に適合しており、料理や掃除、毛染め、介護など多用途で活躍。繊細な作業を快適に行いたい方におすすめです。
SANYU ニトリル手袋 ホワイト(100枚)
厚手で破れにくく、滑り止め加工が施された高耐久のニトリル手袋です。食品衛生法に適合し、調理や食品加工の現場でも安心して使えます。
ラテックスフリーでアレルギー対策にも対応し、指先の感覚を活かせる設計で長時間の使用でも快適です。
Duerfusa ニトリル手袋 ブラック(100枚)
国内検査機関で食品衛生法に適合しており、飲食店や食品加工の現場でも多数使用されています。高い伸縮性と耐久性を持ち、破れにくく快適な着け心地を実現。
粉なしで肌にもやさしく、長時間作業でも手が疲れにくいプロ品質のニトリル手袋です。
DAISSHO ニトリル手袋 ブルー(100枚)
厚さ約0.07mmの薄型設計で手にしっかりフィットし、指先の細かい動きにも対応します。エンボス加工により滑りにくく、調理や清掃に最適。
食品衛生法適合でラテックスアレルギーにも配慮された素材を使用しており、安全性と快適性を両立しています。
ショーワ ナイスハンド きれいな手(100枚)
やわらかく手にフィットする天然ゴム製の極薄手手袋です。粉なしでもスムーズな着脱が可能で、細かい作業にも対応します。
環境に配慮したFSC認証の原材料を使用しており、品質だけでなくサステナビリティにもこだわった調理用手袋です。
ファーストレイト ニトリルグローブSP3(150枚)
人気のソフトパープルカラーで、しなやかな伸縮性と高いフィット感を実現した手袋です。指先には滑り止め加工が施され、細かい作業もスムーズにこなせます。
パウダー・ラテックスフリーの合成ゴム製で、アレルギー対策にも配慮された安全性の高い製品です。
ニトリル手袋(使い捨てのゴム手袋)があるとミンチ使う料理とかは手全体を道具として使えて、肉だの魚だの手洗いが大変な料理は脱げば手洗いもほぼ不要で、はたまた雑菌を極力入れたくない多人数の料理とかは安心感があり、大活躍なので一箱台所にあると便利です pic.twitter.com/SzcLvOtfGO
— 恥とテキスト(ゴミひろうムスカ大佐) (@kuchinashi321) December 5, 2024
前から皿洗いとか風呂掃除の時はゴム手袋してたんだけど、そもそも1番手を洗うのって料理してる時だな?と気づいて、料理中も使い捨て手袋するようにしたら手荒れだけでなく、めっちゃ酷かった爪割れが改善した。爪も乾燥してたんだね…
— しましま(2ヶ月で1.6kg落とす) (@shima_ryo_iku) January 7, 2025
調理用手袋のメリットとは

衛生面の向上
調理中の手には、見えない細菌やウイルスが多く存在しており、手洗いをしていても完全に除去することは難しいのが現実です。手袋を着用すれば、これらの雑菌が食材へ直接移るのを防げるため、家庭でも飲食店でも清潔な調理環境を保つ手助けになります。
このような衛生対策は、特に生肉や生魚、加熱前の食品を扱う場面で重要です。食中毒の原因となる菌やウイルスは、目に見えないだけに、調理者自身が気づかないうちに他の食材へと広がってしまうことがあります。そのリスクを下げるためにも、手袋の活用は非常に有効です。
手荒れやアレルゲンからの保護
調理用手袋には、手肌を守るという明確なメリットがあります。毎日の調理で頻繁に水や洗剤、食材に触れることは、手にとって大きなストレスです。とくに乾燥肌や敏感肌の方は、すぐに手が荒れてしまうこともあります。手袋を着けることで、これらの刺激を遮断できるため、手荒れ防止につながります。
さらに、香辛料や果物の酸など、刺激が強い食材を扱う際にも手袋は有効です。これらの成分が肌に触れると赤くなったりヒリヒリすることがありますが、手袋をしていればダメージを回避できます。つまり、手袋は「食材のため」だけでなく「自分の手を守るため」にも重要な道具だと言えます。
臭いや汚れの付着防止
調理後に手に臭いが残ってしまった経験は、多くの人が持っているはずです。特にニンニク、魚、玉ねぎ、カレーなどの食材や料理は、洗ってもなかなか臭いが取れません。こうした臭いの付着を防ぐのに、調理用手袋が役立ちます。手に直接触れないことで、臭いの元になる成分が肌に移らないからです。
また、臭いだけでなく、色移りや油汚れにも対応できます。例えば、カレーのターメリックは皮膚に染みつきやすく、食材によっては手が赤く染まってしまうこともあります。手袋をしていれば、そのような心配をする必要がなくなります。
さらに、爪の間に入り込む汚れも防げます。調理中は気づかないうちに細かなゴミや食材のカスが入り込み、見た目にも不衛生になってしまうことがあります。こうした点でも、手袋は衛生と清潔感を保つための有効な手段となります。
来客・業務用としての信頼感
飲食業やテイクアウトを行うお店にとって、調理用手袋の使用は“信頼を得るためのひとつの演出”ともいえます。お客様からすれば、素手で調理された料理よりも、手袋を着用して衛生管理を徹底していると見える料理の方が、明らかに安心できるからです。とくにオープンキッチンでは、その印象が顕著に表れます。
さらに、企業や店舗では食品衛生法や社内ルールにより手袋の使用が義務化されていることもあります。安全面だけでなく、「見せる清潔さ」を意識することは、ブランドイメージや口コミにも影響する可能性があるのです。
来客時の家庭料理においても、手袋をして調理する姿勢は「清潔さへの配慮がある人」という好印象につながります。
食材ごとの使い分けが容易
調理現場では、異なる食材を同じ手で触ることで菌の交差汚染が起こるリスクがあります。これを防ぐ方法のひとつが、手袋を食材ごとに使い分けることです。使い捨てタイプであれば、1回の作業が終わるごとに手袋を外して新しいものに取り替えるだけなので、とても手軽です。
例えば、生肉に触れた手袋を野菜に使い回すことは、食中毒の原因になります。ですが、手袋をこまめに交換していれば、このようなリスクを未然に防ぐことができます。とくに飲食店やお弁当製造では、この意識が徹底されています。
調理用手袋のデメリット
手にフィットしない場合の作業効率低下
調理用手袋が手にフィットしていないと、作業のスピードや正確さが落ちてしまいます。サイズが合っていない手袋を使うと、指先に余りが出たり、生地がたるんでしまったりして、細かい動きがしづらくなるのです。
このような状態では、包丁を持つ手が不安定になったり、食材をうまく掴めなかったりすることがあります。特に、薄切りや飾り切りなど、繊細な作業を行う際には大きなストレスになりかねません。また、手袋がずれて作業中に何度も直す必要があると、無意識のうちに集中力も削がれてしまいます。
さらに、作業が遅れるだけでなく、ケガのリスクが高まるという点も無視できません。安全面の観点からも、手に合ったサイズの手袋を選ぶことは非常に重要です。
手が蒸れる・汗をかく不快感
調理中に手袋を長時間つけていると、内部が蒸れて汗をかきやすくなることがあります。この状態が続くと、手がベタついたり、皮膚がふやけたりして、非常に不快に感じる方も少なくありません。
特に夏場の調理や火を使う場面では、手袋の中が高温多湿になりやすく、ムレによるストレスが大きくなります。手袋を頻繁に取り替えられない状況では、集中力が削がれるだけでなく、作業への意欲も下がってしまうでしょう。
このような不快感を軽減するには、作業の合間に手袋を外す習慣を取り入れることです。一つの作業が終わるごとに短時間でも手袋を外して手を乾かすことで、ムレを防ぎ、手肌をリフレッシュさせることができます。
調理用手袋の選び方

用途に応じた素材選び(ニトリル・ポリエチレンなど)
調理用手袋を選ぶ際には、使用する目的に応じて素材を選ぶことが大切です。素材にはいくつかの種類があり、それぞれ特性が異なります。
ニトリル手袋は、耐油性や耐久性に優れており、肉や魚など油を多く含む食材を扱う調理に向いています。手にフィットしやすく、細かい作業にも適している点が特徴です。
ポリエチレン手袋は、薄手で着脱がしやすく、短時間の作業に適しています。耐久性は低めですが、簡単な仕込みや盛り付けなどには十分対応できます。
どの素材にもメリットとデメリットがあるため、使用頻度や作業内容に合わせて選ぶことが重要です。
サイズのフィット感
調理用手袋を選ぶうえで、もっとも基本的でありながら軽視されがちなのが「サイズのフィット感」です。見た目にはさほど大きな差がないように感じるかもしれませんが、実際に作業に取りかかると、ほんのわずかなズレや締めつけが想像以上にストレスになります。
サイズが合わないと、手袋の中で手が動いてしまい、包丁や調理器具をしっかり握ることができません。結果として、力が入りにくくなったり、調理中に手袋がずれて集中力が切れてしまったりします。細かい作業が要求される場面では、このような不快感が大きな作業効率の低下に直結します。
さらに、指先の余りが気になるときには、思わぬタイミングで手袋が食材や器具に引っかかることもあり、ケガや調理ミスの原因にもなり得ます。一方で、きつすぎる手袋は血流を圧迫し、長時間使っていると手がしびれたり、早く疲れてしまうこともあります。
そのため、手袋を購入する際には「なんとなくの感覚」ではなく、自分の手のサイズにしっかり合ったものを選ぶことが大切です。多くの商品はS・M・Lといったサイズ展開がされているため、最初に自分の手の幅や長さを計測してから選ぶと失敗が少なくなります。
パウダーフリーかどうか
調理用手袋を選ぶ際に、多くの人が見落としやすいのが「パウダーフリーかどうか」です。この違いは見た目では判断しづらいものの、実際の使用感や安全性に大きく関係してきます。
一般的に、パウダー入りの手袋は、着脱がしやすく滑りも良いため、医療や清掃などの現場で使われることが多いです。しかし、調理という視点で見ると、このパウダーが問題になることがあります。パウダーの粒子が食品に付着すると、食材の風味を損なうだけでなく、粉を吸い込んでしまう可能性もあり、衛生面で不安が残ります。
また、肌が敏感な方にとっては、パウダーが刺激になることも少なくありません。手荒れの原因になったり、かゆみや赤みを引き起こしたりと、肌トラブルの要因にもなり得ます。これを避けたい場合には、最初から「パウダーフリー」の製品を選ぶことが安心です。
現在では、パウダーフリーでありながらも装着しやすいように工夫された手袋が多く販売されています。内側に滑りやすい加工を施していたり、伸縮性に優れていたりと、使用感を損なわない製品が増えてきています。
食品衛生法に適合しているか確認
調理用手袋を購入する際、必ず確認しておきたいのが「食品衛生法に適合しているかどうか」です。これは、その手袋が食品に直接触れても安全かどうかを示す基準であり、調理に使う道具としては欠かせない視点です。
食品衛生法に適合した製品には、「食品衛生法適合」「食品接触可」「厚生労働省告示第370号適合品」などの表示がパッケージや商品説明に記載されています。これらの表記があることで、有害な化学物質が手袋から食材に移る心配がないことが示されています。
反対に、この表示が見当たらない手袋は、工業用や掃除用に作られている可能性があります。こうした手袋は、油や薬品には強いものの、食品との接触を前提としていないため、調理に使うのは非常に危険です。知らずに使用すると、食材への異物混入や健康被害を引き起こす可能性があります。
家庭用であっても、安心して料理を楽しむためには、信頼できる製品を選ぶことが基本です。
調理用手袋の使用ポイント

食材ごとに手袋を交換する
調理用手袋を使う最大の目的の一つは「交差汚染」を防ぐことにあります。交差汚染とは、ある食材に含まれる菌や汚れが、別の食材に移ってしまうことです。これを避けるためには、食材ごとに手袋を交換することが基本となります。
たとえば、生肉を触った後にそのまま野菜を扱ってしまうと、加熱されていない野菜に菌が付着する可能性が高くなります。これは家庭だけでなく、飲食店や給食の現場などでもよくあるリスクです。どれほど丁寧に調理していても、手袋を交換しなければ意味がありません。
この行動を習慣化することで、家庭でもプロと同じレベルの衛生管理が可能になります。時間や手間がかかるように思えるかもしれませんが、安全を守るための基本的な対策としてぜひ徹底したいポイントです。
着脱の前後には必ず手を洗う
調理用手袋を使うことで手は保護されますが、その前後に手を洗わなければ本来の効果は十分に発揮されません。手袋の内側に汚れや菌が入り込んでしまえば、表面だけを清潔に保っても意味がないからです。
着用前に手を洗っておくことで、手袋内部が清潔に保たれます。また、脱いだ後に手を洗うことで、手袋を通じて触れたかもしれない細菌を落とすことができます。とくに調理の合間にスマホやドアノブなど他の物に触れた場合、知らないうちに手が汚れている可能性があるため、手洗いは欠かせません。
見た目ではわからない汚れや菌の存在を考えると、手袋をしていても「素手と同じように手を洗う」という意識が必要です。これは家庭でも業務でも共通する、衛生管理の基本的な考え方です。
長時間使用しない(こまめに交換)
調理用手袋は一度装着したら、つい長時間使い続けてしまいがちです。しかし、手袋の内側は時間が経つにつれて汗や皮脂で湿り、菌が繁殖しやすい環境になります。このため、長時間の使用はおすすめできません。
手袋が湿った状態になると、肌がふやけて不快になるだけでなく、外からの菌も繁殖しやすくなります。また、手袋自体が傷んで破れやすくなることもあるため、衛生面と安全性の両方でリスクが高まります。
こまめに交換することで、常に清潔な状態を保つことができ、快適に作業を続けることができます。特に、複数の工程をこなす料理や、長時間キッチンに立つ場合には、一定時間ごとに新しい手袋に替える習慣をつけると安心です。
高温調理時は耐熱性のある手袋を使う
通常の調理用手袋は、細菌や汚れから手を守ることには適していますが、高温には対応していません。熱い鍋や天ぷら油に触れるような場面では、耐熱性のある専用手袋を使用する必要があります。
そのまま薄手の手袋で高温の調理器具を持つと、すぐに熱が伝わり、やけどの危険性が高くなります。見た目には大丈夫そうに見えても、素材によっては一瞬で溶けたり縮んだりする場合もあるため注意が必要です。
耐熱手袋は厚手で滑り止め加工がされているものが多く、安全性を保ちながら作業効率も確保できます。用途に応じて使い分けることで、調理中の事故やケガを防ぐことにつながります。
保管は直射日光や高温多湿を避ける
調理用手袋を長く衛生的に使うためには、保管方法にも気を配る必要があります。直射日光の当たる場所や湿気の多い場所に置いておくと、手袋の素材が劣化しやすくなり、破れやすくなったり、変形したりすることがあります。
特にビニールやニトリルなどの素材は、熱や光に弱い性質を持っていることが多く、長時間の放置によって弾力がなくなったり、粘着質になってしまうことがあります。また、湿気の多い場所ではカビや雑菌が繁殖するリスクも高まります。
手袋はなるべく風通しのよい、涼しくて乾燥した場所に保管することが理想的です。元のパッケージに入れて密封しておくと、ホコリや汚れから守ることもできます。使用頻度が高い場合でも、品質を保つことで毎回安心して使用できる状態を維持できます。
まとめ:料理に安全な「調理用使い捨て手袋」おすすめ10選
調理用手袋は、衛生面の管理から手肌の保護、作業効率の向上に至るまで、多くのメリットを持つアイテムです。日々の料理や食品を扱う場面で、どのような手袋を選び、どのように使うかによって、安全性や快適さは大きく変わります。
この記事が、あなたの目的や環境に合った手袋選びの一助となれば幸いです。
ぜひ今回の情報を参考に、使いやすく安心できる一枚を見つけてみてください。清潔で快適な調理環境づくりを、今日から始めましょう。








